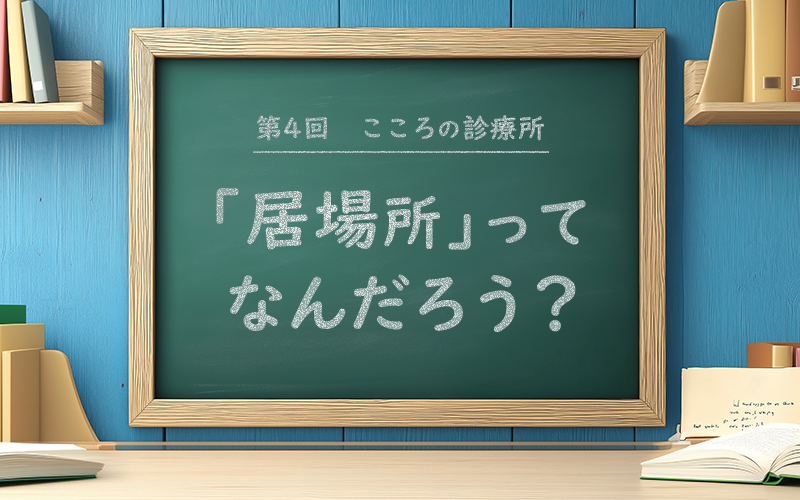私は昔から「ひとりでいることが楽な場所」が大好きでした。人に囲まれて賑やかに過ごす時間を楽しく感じる人もいると思います。
でも、私は学校に行くのも苦手、人と会って話すことにもストレスを感じてしまう、そんな子どもでした。だからこそ、誰にも気をつかわず、静かに自分らしくいられる空間があると、心がほどけて安心できる。そうした思いが、私にとって「居場所」という言葉の原点になっています。
在宅診療に携わっていると、病気や障がいだけではなく、「どこにも自分の居場所がない」と感じて苦しんでいる方に出会うことが少なくありません。ひきこもりの若者、不登校の子ども、孤独を抱える高齢者…。
心の奥で「自分はここにいていいのだろうか」「今、生きている意味はなんだろう」などという不安を抱えています。その姿に触れるび、居場所があるかどうかが人の心や生活に大きな影響を与えるのだと実感します。
居場所があることで、人は少しずつ変わっていきます。最初は隅の椅子に座って何も話さなかった人が、やがて「おはよう」と声をかけてくれるようになる。小さな変化の積み重ねが、その人の生きる力を取り戻していくのです。
けれども一方で、居場所は「変わらなくても幸せでいられる場所」でもあります。
誰とも話さずに本を読んで過ごすだけでもいいし、ただぼんやりと人の気配を感じているだけでもかまわない。そこにいるだけで安心できる、そんな場所が人を支えてくれるのです。
だから居場所には「その人らしさ」が自然とにじみ出ます。人によっては笑顔や会話かもしれませんし、静かな沈黙や穏やかな時間かもしれません。どちらも大切で、そのままが尊重される空間だからこそ、その人が自分を押し殺さずにいられるのだと思います。
こうした思いから、私たちはNPOを立ち上げ、「居場所づくり」を始めました。そこでは勉強をしてもいいし、就労体験をしてもいい。けれど何もしなくても大丈夫。自分のペースで過ごせる柔らかな空気を大事にしています。
そして「ここに来ればひとりじゃない」と思えるだけで、人は安心し、また歩み続ける力を得られるのです。
居場所は、派手なものでも、特別な施設でもありません。むしろ小さな安心の積み重ねこそが、人を生きやすくし地域全体を温かくしていきます。変わることも、変わらないことも、その人の大切な物語の一部。そんな物語を受け止められる居場所を、これからも広げていきたいと願っています。
このような取り組みに対して、行政による制度がないからこそ、いろんな方々とのご縁による地道な応援もお待ちしております!
居場所に関するおすすめ作品2選
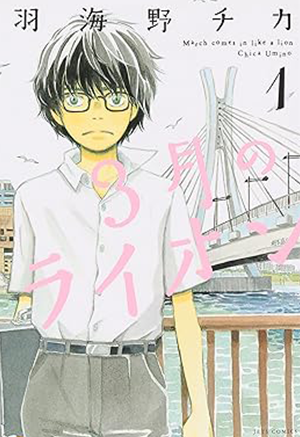
『3月のライオン』
羽海野チカ 白泉社
孤独を抱える若い棋士・桐山が、温かな川本家との出会いを通じて「居場所」を見つけていく物語。
厳しい将棋の世界で傷つきながらも、人に受け入れられることが心を癒し、新しい力を与えてくれる過程が丁寧に描かれています。居場所とは成果を出すための場所ではなく、ありのままの自分を認めてもらえる空間と気づかせてくれる、穏やかに深い余韻を残す作品です。

『いちご同盟』
三田誠広 集英社文庫
不登校や病気を抱えた高校生たちが出会い、互いに支え合うことで「生きる意味」と「自分の居場所」を探していく物語。重いテーマを扱いながらも、清々しく読みやすい文体で綴られており、若い世代はもちろん大人にも響きます。誰かとつながることで、孤独の中にも居場所が生まれることを伝えてくれます。